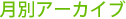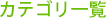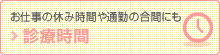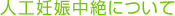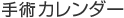最近、吉村昭さんという作家の「雪の花」という小説を読みました。江戸時代の医師が天然痘のワクチン接種普及に生涯をささげる実話に基づいた話でしたが、そんな折、日本にもサル痘が上陸したとのニュースがあり、この小説とも重なって未だ現代にも撲滅した天然痘が残っているということに驚きました、
もともと18世紀中ごろイギリスのジェンナーが、牛の乳しぼりの女性が「牛の」天然痘に感染すると、かさぶた程度の軽い発疹で治癒し、以後「ヒトの」天然痘にかからないという話から、数多くの実験を経て生ワクチン接種の方法と理論を確立したことに始まり、日本では、長崎の出島に西洋の医師が持ち込み、全国に広まっていくわけですが、当然、現在のような精製したワクチンを凍結させて空輸できるというわけではいので、運ぶのが大変です。まずは牛痘のウイルスのついたかさぶたや膿(痘苗)を子供に接種し、その子供のさらにできたかさぶたを、次の子供に接種、さらに次の子供、次の子供にということをつないで、生ワクンが不活化しないように運んでいかなければならない。
主人公は京都まで運ばれたほぼ全滅状態の膿(痘苗)から、やっとのことで不活化していない膿(痘苗)を手に入れ、そこからこれを福井まで運ぶという話なのですが、深い雪の中を、常に子供連れ(接種を繋いでいくために)で徒歩と馬で何百キロも旅していくという、とてつもなく大変な仕事を成し遂げます。ところがいざ福井まで運んだ後も、当時、一般の人に免疫やワクチンの知識はないので、天然痘が流行した際の悲惨な現実は知るものの、牛のウイルスの付着した痘苗とやらを我が子に植えるなどということに抵抗があり、なかなか普及しません。
さらに漢方医と蘭学を学んだ西洋医との間の確執や、行政の抵抗まで加わり、せっかく福井まで運んだワクチンが次の子供に接種できず、これ以上つながらなければ、生ワクチンが死滅してしまうという瀬戸際まで、主人公は追い込まれます。
最終的に、権威ある医師たちの協力も得て、行政も動き、なんとかワクチンの普及が成功し、現代にいたっていくわけですが、あらためて並々ならない主人公の信念と勤勉と苦労に敬意を払わずにおれない、感涙の一作でした。